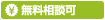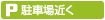弁護士法人兼六法律事務所は「法的サービスの提供を通じて社会を幸福にします」を事務所理念とし、気軽に何でも相談できる弁護士、法律事務所を目指しています。
交通事故、医療過誤、消費者被害(先物取引・証券取引など)、自己破産、債務整理、企業再生、離婚、遺産分割、遺言、刑事弁護など、7名の弁護士が誠心誠意、相談に応じます。
取り扱い分野や弁護士報酬などに、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
□■【 弁護士法人 兼六法律事務所 】公式サイトはコチラ■□
 ■離 婚
■離 婚
▶
離婚一般
離婚したいと思った時、何を決めればいいのか、どのように話を進めていけばよいのかについて、ご説明致します。
1.離婚する際に決めておくべきこと
a.親権者
未成年の子の親権者を決めないまま離婚することはできません。
早く離婚したいために、とりあえず親権を相手に渡す方がいますが、親権者を変更することは例外的な場合にしか認められていませんので、慎重に決める必要があります。
b.養育費
子どもを監護養育していない親が、子どもを監護養育している親に対して支払うものです。
養育費の額は双方の収入によって決められます。夫の年収が500万円で、妻の年収が200万円、妻が小学生の子ども2人の親権者になる場合、妻がもらえる養育費の額は月6万円程度です。
c.面会交流
子どもを監護養育していない親と子どもとが会うことを面会交流といいます。頻度や面会時間、場所等をあらかじめ決めておくことが望ましいです。
d.財産分与
夫婦で築いた財産を分けることができます。妻が専業主婦で、収入がなくても、内助の功で、夫の財産に対する貢献が認められますので、多くの場合、夫の財産の2分の1を分与するように求めることができます。
相続で得たものや、婚姻前の財産は分与の対象にはなりません。
e.年金分割
婚姻期間中の厚生年金記録・共済年金記録を分割することができます。
平成20年4月1日以降に結婚された場合は、分割の割合を決める必要はなく、社会保険事務所に請求することで、平成20年4月1日以降の厚生年金記録・共済年金記録を2分の1に分割できますが、それ以前の記録については、分割の割合を決める必要があります。
f.慰謝料
慰謝料は、離婚に至る原因が相手にある場合に請求できるもので、婚姻期間や離婚の原因によって金額に幅がありますが、100万円程度から300万円程度のことが多いです。
2.離婚の進め方
a.協議離婚
以上のようなことを夫婦間の話し合いで決めることができれば、離婚届けを役所に提出することで離婚することができます。
養育費、慰謝料、財産分与については、公正証書で取り決めをしておくと、万一、相手方が支払を怠った場合でも、すぐに強制執行することができます。年金分割については、公正証書か公証人の認証した夫婦間の合意文書を作成することが必要です。
b.調停離婚
夫婦間での話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停をします。
調停というのは、調停委員を通じて話し合いをする手続きで、夫婦が顔を見合すことなく、話をすすめることができます。
調停の中で決めたことは、家庭裁判所が調停調書という書面にまとめてくれます。調停証書は、確定判決と同じ効力がありますので、相手方が金銭の支払を怠った場合は、強制執行をすることができます。
c.裁判離婚
調停をしても話がまとまらなかった場合は、裁判をする必要があります。
裁判で離婚が認められるためには、相手方の不貞、悪意の遺棄、その他暴力など婚姻を継続し難い重大な事由がある等、法律で定められた離婚原因が必要です。
3.離婚に付随する問題
別居を始めたものの夫が生活費を入れてくれないということがあります。そのような場合は、生活費を請求するための調停を起こすことができます。生活費の額は、双方の収入、子どもの有無、年齢等によって決まります。
また、別居を始めたが、夫が追いかけてきて暴力を振るうのではないかと心配な場合は、地方裁判所に保護命令を申立て、妻に近付かないように命令してもらえることもあります。
離婚する場合は、いろいろな問題を解決していかなければならないので、一人で抱え込むのは大変です。
弁護士に相談されることをお勧めします。